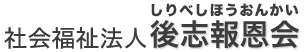福祉の里づくり
自分史でつづる銀山学園
「福祉」への助走
故野村 健(名誉会長・元銀山学園施設長)が、自らを振り返りつつ『福祉の里づくり』の夢を描いてきた想いがつづられています。この想いは現在も、社会福祉法人後志報恩会の理念として継承され日々の実践の礎となっています。
平成5年10月発行 ぎんざんだより100号
銀山学園長 野 村 健
自分史でつづる銀山学園
障害をもつ人ももたない人も、弱者も強者も、自分も他者も、みんなでつくる幸福への道
「福祉」への助走
-懊悩を繰り返した青春時代
法があって人間があるのではない
人間があって法があるのだ
私は、法が優先されなければならない職場を去り、より人間らしい生き方、
より人間らしい幸せを求めて、今、知的障害者と生きる
福祉へのめざめ
私が福祉の仕事を志向していったのは、幾つかの理由がある。その主なものは、父が北海道行政を通して早くから福祉の仕事をしていたということと、私自身、青春時代に病気と吃音で悩み、その悩みを通して福祉を志向していったといえる。特に吃音の悩みは、私の人生観の土台を形成してくれたと思う。私の好きな言葉に「人生とは芸術である。芸術とは創ることである。人はみな芸術家である。」という鈴木大拙翁の言葉がある。私は青春時代に、人間の幸福を少しでも創造してみたいと願った。この願いの灯が未だ消えず、私の心に沸々と湧き出させてくれているのは、実にこの青春時代に味わった苦しみの結晶にほかならない。
吃音を真剣に気にし悩み始めたのは、私が小学校6年生の時であった。級長をしていた私は、教壇に上がらされて物語をしているうちに「かじか」の「か」がどうしても言えなくなり、焦れば焦るほど顔が真赤に硬直して、口をパクパクさせてクラスメイトから笑われ、恥ずかしさでめまいしそうになったことに始まる。
吃音の苦しみは、高校1年になって肺を患った私に一層重くのしかかってきた。自宅療養をした私は、1年間節穴(・・)のある天井を見つめ、吃音に悩みながら「人間って何なのだろう」と考え始めた。今でこそ生命の起源の仮設はあるが、当時はまだなく、要は分からないことを一生懸命考えていたのである。そうしてようやく分かったことは、生命の起源ではなくて「自分はいずれ死ぬのだ」という自然なことであった。そこで、どうせ死ぬのなら安らか(・・・)に(・)死にたい(・・・・)と願い、安らかに死ねるために、人を傷つけないで生きようと考えたのである。
このように、他者とのかかわりで自分の人生を考え始めたのは、一般にアイデンティティが確立されるといわれる青年期であった。はからずも仏教でいう生・老・病・死の四苦のうち、病を通して生・死のほんの一端を考えさせられたわけである。勿論この観念的な思いは、復学して弟と同期で学ぶようになっても、吃音が治っていない私に、少しも生きる自信を与えてはくれなかった。
寝ている時しか吃音の苦しみを忘れる事のできなかった私は、一生懸命に自分の悩みをありのままにノートに書くようになっていた。初めは、人に言えない自分の苦しみをありのままに書くことは恥ずかしく、もし人に見られたらどうしようという不安に怯えていたが、やがてその不安と闘いながら、少しずつ自分の不安な思いを、ありのままに表現できるようになった時、少しは心に安らぎが戻った。そんなことから束の間ではあったが、短歌に興味を持ち、第一作を思いきって新聞に投稿してみたことがある。
廃人と ともに語りて 笑いしが
すぐ後にくる 暗きは真顔
自分の名前が生まれて初めて新聞の活字になった喜びは、今でも脳裏に刻まれているが、それも生きる自信を与えてくれるものではなかった。
母は心配して、私を東京の吃音矯正所にやらせてくれたが、治らないまま悶々とした日々が続いた。そんな姿を見て母はよく「気にしなさんな」と優しく慰めてくれたものだが、気が立っていた私は「気にしない方法を教えろ」と口答えして母を困らせたものだ。精神的な悩みとは、悩む根源を気にしなければよいわけであるが、そう頭でわかっていても、気にして悩まざるを得ない自分との闘いが悩みであった。「悩みを通して光に至る」というロマン・ロランの境地に、どうしたら到達できるのかを思いあぐんだが、どうしても実感として理解するまでに至らなかった。私は矯正所で学んだ丹田呼吸を一日何時間も行い、吐く息、吸う息に精神を集中させるという訓練を繰り返した。何年も続けているうちに、その時間だけは吃音の苦しみを忘れることができ、心は深く安らいでいった。
しかし、未熟な私は吃音を気にする自分から抜け出すことができず、劣等意識から絶望感へ、絶望感から虚無感へ、虚無感から自己否定へと自らを追い込んで行った。アドルムを枕許にしのばせながら、飲むか飲まないかを決断する夜を幾日も過ごした。私の場合、精神的懊悩の終極は「生か死か」の二者択一だった。死ねなかった私は、生きるより道がなかった。その時私は、自分に対して「どんなに苦しくても自ら(・・)の(・)力(・)で生きること」他者に対しては「痛みを分かち合って共(・)に(・)歩む(・・)こと」を実践していこうと強く心に誓った。その自らの誓いを徐々に実践できるようになった時は、ようやく自分の悩みから決別することができたのである。思えば10年の歳月が流れたことになる。
人間の心の幸せは、悩みを通して自分に合った方法で、心底から納得できた時に生まれるものなのだろうか。
私は、ギリギリのところで選択した思いを、精神的支柱と呼びたいのであるが、精神的支柱とは苦しい時に、その思いへ帰っていける「心のふるさと」のような気がしてならない。信仰の道に入れなかった私は、このようにして他者への依存を捨てて、自らが精神的に自立していく努力の中に、心の幸せが成熟していくものであることを、また自分の幸せは、決して自分だけの満足-利己の中に生まれるものではなく、他者への思いやりの中に生まれるものであることを、ささやかではあるが体得させてもらったのである。この思いは、今なお私の心に脈々と波うっている。
このような生きざまの中で、私に福祉観たるものがあるなら、精神的には吃音と病気で学んだこと、環境的には福祉の学校で学び、福祉事務所で14年間ケースワーカーとして働かせてもらった経験の中に育まれ、今、知能に障害を持った人たちと生き、その命の尊厳と幸せを願うことによって、熟成させつつあるといえる。
福祉事務所からみた福祉
こんなこともあった。札幌市内の東西を二分する、豊平川の河川敷に住む人からの生活保護の申請で、調査に訪れた時の事である。敷地に足を一歩踏み入れると、突然大勢の人たちに囲まれ尋問された。敵意のないことを分かってもらえて、初めて案内された掘立小屋は、ドアの代わりにむしろ(・・・)が垂れ下がり、6畳ほどの広さの板の間には、うす汚れたゴザが敷かれており、昼間でも電気が欲しいほどの暗さだった。目が慣れるにつれ、ノミが飛び回っていることに気づき、急に全身がむず痒くなっていく錯覚に襲われながら、重症の肺結核に悩む人の話を聞いた。咳込みながら入れてくれたお茶を、おそるおそる、感染の可能性が充分にある事を知りながら飲み干した。「なぜ、こんな惨めな所に人が生活しなければならないのか」というぶつけようのない怒りの中で、せめて私ができたことは、悩める人の心の痛みを少しでも共有することだった。
当時のケースワーカー(生活保護担当者)のなかには、権力的な立場で「お前は働けるのだから生活保護をもらわないで働け」と一方(・・)通行(・・)する人たちがいた。それは人間にとって悲しい事である。その悲しみは、される立場になって初めて分かる事なのだと思う。14年間、未熟ではあったが、生活保護を通してさまざまな人たちと出会い、その中でケースワーカーにとって最も大切だと思った事は、生活に困っている人の立場に立って、その痛みを共有しながら、共に歩む、ということだった。しかし、福祉事務所は機能的に法的規制を受けやすい。そのことは、人間のより総合的な幸福を考えていった時、その考えを実現化していくことを拒む限界であった。そんな状況の中で、私は人間より人間らしく生きられるために、人間の幸福を考え、その考えが少しでも実現できる場を求めて、14年間世話になった職場の人々に感謝の念を抱きながら別れを告げ、知能に障害を持った人たちの福祉施設・銀山学園の創立へと旅立ったのである。
平成5年12月発行 ぎんざんだより101号
銀山学園長 野 村 健
福祉の里づくりを夢みて
障害があってもなくても
人間には変わりがない
だから知的に障害がある人もない人も
より人間らしく生きられる
地域社会-福祉の里を
知的障害者も自分も参加して
皆で一緒に創りたい
学園創設期の夢
-知的障害者の楽園をつくりたい-
北海道福祉の名門、札幌報恩学園の山下充郎先生から、知的障害者の施設をつくるので、施設長になって欲しいと依頼があったのは、私が37歳の時であった。当時、私は札幌市の福祉事務所で、係長という肩書きの仕事をしていた。
北海道で精神薄弱児の施設を最初に創設された方は、札幌報恩学園の山下充郎先生(初代理事長 小池九一先生)と富ヶ岡学園の小池國雄先生(小池九一先生の長男)である。お二人は義兄弟であるが、私は父の縁で幼少の頃から知己を得ていた。
そこで早速、私が最初に就職させてもらった(3ヵ月であったが)富ヶ岡学園の小池國雄先生の所へ相談に伺った。先生は焼酎を飲みながら「火中の栗を拾うようなものであるが、やる気があるなら是非やってみろ」と言われ、私は銀山学園創設の旅立ちを決意していったのである。昭和44年(1969年)10月、稔り豊かな秋であった。
幸せなことには、未知の世界への旅立ちは37年の人生で最も信頼できる男、山﨑忠顯(現在、同じ法人の和光学園施設長)と共にすることが出来たことである。彼は、札幌市役所で勤労青少年の余暇指導にあたっていた柔道3段(現在5段)の好男子で、弱冠27歳であった。
厳冬の2月、道都札幌市から車で2時間揺られて出会ったのは、雪にすっぽり姿を隠し、赤い屋根だけが、純白の雪の中にくっきりと浮かんでいる光景だった。建設中の銀山学園との出会いである。周りには殆ど人家がなく、まさに開拓の地にふさわしい、標高200メートルの原野が広がっていた。
銀山市街にある、高橋賢吾さん宅に草履を脱がせてもらった私たち2人は、開園の5月に向けて職員と入園者70名の募集から始めなければならなかった。好運なことに私たち2人の旅立ちは、4大新聞が大々的に報道してくれたので、全道各地から職員も入園者も集まって来てくれた。
創設当初の夢、それは140ヘクタール(42万坪)の大地に、知的障害の人たちと共に生きる楽園を創造することだった。
1970年5月15日、銀山学園は産声をあげたが、吉幾三さんの歌の文句ではないが、金もない、設備もない、あるのは借金だけ。おまけがついて風が吹けば停電し、雨が降らないと断水し、食事も入浴にも困る始末だった。近所を流れる小川から、水をバケツリレーして、急造の五右衛門風呂に入所者70人に入ってもらったり、加工食品を頼りに陸の孤島のような生活をした日々の想い出は、今となっては懐かしい想い出である。
どんなに苦しくても、知的障害者の楽園をこの大地に創造してみたい。そんなロマンだけが私たちの心を支えてくれていた。
福祉への発想が変った
-福祉の里をつくりたい-
入所者70名(翌年70名増員)と私と山﨑事務長は、寝起きを共にしていた。道内15番目の大人の施設(現在は200を超えている)として誕生した当時の入園者は、非行で他施設では入所を断られたり、無理に離婚させられ本人が入所を拒否しているのに、施設へ捨てるように置かれてしまった人もいた。また、保護観察中の人や婦人更生相談所等で困り果てた末、依頼があり入所して貰った人たちが沢山いた。腹が立つこともあった。でも、福祉施設(・・)は福祉の最後の砦であると思い直して、爆発しそうな感情を何度も抑えたものだ。
創立期の苦しさは、創立した者にしか分からないのかもしれない。何もない所からの出発である。それだけに職員は苦労の連続だったと思う。よく耐え頑張ってくれたと、今振り返ってしみじみと思う。しかし、誰よりも辛かったのは入園者である。私たち職員は、福祉に情熱を燃やしていれば耐えられる。しかし、入園者はそうはいかない。施設生活がどんなに嫌でも、社会や家庭に戻れない人たちは、生涯、施設で生活しなければならないのである。
未熟だった私は、管理的な立場だけの自分の大変さに翻弄され、入園者の本当の苦痛を知るのに3年の月日を要した。
入園者の最大の苦痛、それは「施設にいたくない」ということだった。
施設生活には選択できる自由が殆どない。また、食事や入浴や寝る場所も拘束されている。そんな状況の中で、当時入園者の無断(・・)外出(・・)が続出したのは、今思えば当然といえる。しかし、この当然といえる外出行動が、管理的な立場から見るとひとつの事件(・・)になるのである。
真夜中に何度も探し回ったものだった。発見できた時の喜びは、何ものにも代えがたい喜びに変わったものだ。施設は常に入園者の事故と隣り合わせているからである。
無断外出があるたび、ケースワーカー出身の私は、その原因を個人や施設内環境の問題として、その対策を考えた。無断外出の常習者K君やA君は、児童施設入所時に10数回の無断外出歴があった。親との関係を重視し、担当指導員に全道各地に走ってもらったり、作業能力のある2人に、作業を通して意欲付けや自信付けなどを試みたが、あまり効果がなかった。
そんな時、試行錯誤を続ける私たちを嘲笑うように集団脱走がおこった。彼らは、地域の人の自転車を盗んで、ドライブインにまで侵入し、遊具を壊し金まで盗んだ。犯罪である。しかし、経営者嘉屋達雄さんの心温かな配慮で、警察沙汰にはならなかった。誠に感謝しても感謝しきれない思いであったが、これ以上、地域のみなさんに迷惑をかけられないという思いで、断崖絶壁に立たされた思いにさせられた。
施設の管理を強化する以外に無断外出をなくす方法はないのだろうか。しかし、管理強化は入園者の立場から見ると、非人間的(・・・・)な対応を意味する。でも、これ以上住民のみなさんに迷惑をかけられない。こんな輻輳(ふくそう)した思いの中で、悩みは極限に達していった。
そんな時、ふと思い出したのである。創設期の僅か6ヶ月であったが、入園者と共に起居していた時のことを。私たち職員は、施設生活の苦痛から解放されるため、入園者を就寝させてから、夜、たまに外出できた。その時見た銀山市街のまばらな人家の灯に「あっ人間が住んでいる」と感動(・・)した(・・)ことを。「そうだ!入園者にもこの感動を味わってもらおう」そんな思いが、私の全身を一挙に駆け巡ったのである。
思えば、札幌在住の時は「すすきの」の繁華街を、歌の文句ではないが「1週間に8日(・・)来い(・・)」みたいに、毎日のようにさまよい歩いたものだった。そんな経験しかなかった私には、田園の夜の灯は、まさに感動として映ったのである。
入園者が地域のご家庭に招かれて、夕食をご馳走になってから、嘘のように無断外出はなくなった。貴重で宝物のような体験だった。
無断外出をなくする方策は「無断外出をなくする方法」を考えるのではなく「外出」ができる方法を考えればよかったわけである。要は、誰の立場に立って考えるか、ということだった。
私と地域との出会いである。
このようにして、創立当初に夢見たドイツのペーテルのような知的障害者だけの楽屋づくりは、わずか3年の月日の流れの中で、施設に居たくない入園者の苦しみを肌で知った時、その夢は忽然と消え、障害のある人もない人も、共に同じ人間として、地域で混然一体に当たり前の生活がしていけるような「福祉の里づくりをしたい」という夢に変っていったのである。
平成6年4月発行 ぎんざんだより102号
銀山学園長 野 村 健
皆でつくる福祉の里
-知的障害者も参加する福祉の里づくり-
地域の人々の理解に支えられて
私たちの願い、それは「知的に障害がある人も、地域の人たちの理解の中で、地域に住み、働ける人は働き、結婚できる人は結婚し、働けない人たちも、まちを自由に散歩したり、家庭訪問や買い物ができる、そんな福祉の里をつくりたい」という夢のような願いである。
そんな夢を胸奥に秘めて福祉の里づくりを始めて17年たったが、ありがたいことには、地域に住んで働いている知的障害の人たちは8人(自宅1人、グループホーム4人、職員寮3人)、また家庭訪問を受け入れている世帯は、80世帯に及んでいる。家庭訪問は全入園者140人を対象に、年5回と自由訪問に分けて実施させてもらっている。このように少しずつではあるが、福祉の里の顔が地域のみなさんのご協力で見え始めてきているのである。
福祉の里づくりの道、それは辛く厳しい道程でもあった。それは、障害者への差別意識との戦いでもあったといえる。施設入所障害者にとって、外出欲求を満たせるのは「施設」ではなく「地域」である。誰もが分かっていることである。しかし、現実は知的障害者を地域社会から疎外しやすい。それは私がぶつかった第一の関門である。福祉の里づくりのためには、このハードルを乗り越えなければならなかった。
乗り越えるための原点、それは「まず自分自身の意識を変える」ということだった。人として生まれてきた以上「どんなに障害が重くても、その前に自分と同じ人間である」というあたり前の意識をもつということである。
当時は知的障害者に対して、社会自立がデイビスをはじめとして、国際的に強調されていた時代だった。したがって「障害」の前に「人間」としての障害者の幸福を考えようとする思想は、日本にも国際的にも波及していなかった。現在、普及され始めているノーマライゼーション思想は1982年からであるから、私たちの福祉の里づくり運動の10年後にあたる。
そんなことから福祉の里づくりは、雲をつかむような状況にあった。最初に試みたこと、それは地域のトップの人たちで構成した「銀山地域を住みよくする会」の創設である。しかし、この会の長老達は、口は出すが実践しようとしなかった。批判するだけで何も生まれてこない。したがって1年で休会を余儀なくされた。それは高寄昇三氏がいう「身近な問題を公的な問題に転化し、解決していこうとする実践的訓練に欠けている」日本市民意識の脆弱さのあらわれであったのだろう。
そこで私は、通称ノッコちゃん(高橋賢彦さん・銀山自動車整備工場主)と共に、地域づくりに共感し合えそうな若人10人程で、半年自宅で酒を酌み交わしながら深夜まで話し合った。最初は、地域づくりの話は一切せず、今の生活や職場のことなどを思い思いに話し合った。そうして最後に農村青年たちが共感し合えたこと、それは今の生活に「生きがいを感じられない」という悲痛な叫びであった。そこで、私たちは「生きがいのあるまち」を自ら参加して創ろうという熱い思いに到達していったのである。
大森 彌氏(東大教授)は「コミュニティが『福祉』と交錯するのは、人間の生きがいにかかわる共同性を共通基盤としているからである」と言われているが、私も同感である。このようにして、今から17年前(1976年)雪残る初春に、誰もが生きがいを感じられる福祉の里づくり母体「あすの銀山を考え行動する会」が燃えるような思いで誕生していったのである。地域づくりに最も必要だったもの、それは人間を大切にしようとする「感性」と「実践力」であった。
2つの実践例だけを紹介したい。
あすの銀山を考え行動する会
・銀山新聞の発行(全世帯300戸を対象)
・柔道の指導(小・中学生対象)
・弓道の指導(青年・婦人・一般)
・囲碁クラブ(園生・一般・小中学生)
・テラコッタ(園生・青年・婦人)
・盆踊り・花火大会・仮装大会 (全住民)
・秋祭り(全住民・行動の会は手づくり出店・植木市・ソフトボール大会・
相撲大会を主管・札幌市の「こぐま座」は4年連続で人形劇の
ボランティア活動をして下さった。
・地区文化祭・家庭教育学級(全住民)
・書道教室(小・中・高・一般)
・カルタ大会(一般)
・児童遊園地づくり
福祉の里づくりエピソード2題
-
町をあげての銀山祭り
「高い!」「高くない!」銀山秋祭りで賑わう出店の「たたき売り場」は、ひと際大きい笑い声が渦巻く。地元の人たちから寄贈された物品を、当園の指導員2人が掛け合い漫才風に次々と売りさばく。「金魚すくい」などの売り場には、飛び入りで地元青年がねじり鉢巻きをして客寄せする。「植木市」には老人の姿もみえる。そば、おでん、焼きとうきびのコーナーでは、女子入園生が愛想よく地元の人たちに応接する。御神輿をかつぎ終わった威勢のよい男子入園者は、学園自慢のホルモン焼きや、地元青年が用意した生ビールで胃とのどをうるおす。町外からは、通称「太鼓のロクさん」こと高田禄郎さんが倶知安町から馳せ参じてくれた。全国に太鼓で名を馳せた禄さん(NHKテレビ「ある人生」に出演、私たちともSTVテレビに出演して下さり、それが縁でキングレコードから、60歳の素人としては全国で初めてのレコードも発売されている)は、入園者の人気者である。札幌からは、国際人形劇にも参加している「こぐま座」(加藤博司代表)もボランティアで、子供や入園者たちの夢を育ててくれた。まさに町内外あげての銀山祭りであった。
-
遊園地づくりに汗を流す
「園長、この土かたいなぁ」農耕班のK君である。知能は小学校4年生ぐらいだろうか。「うん、かたいなぁ。ブルドーザーで固められているからな」児童遊園地のフェンスを埋める穴掘り作業である。「ところでK、今日はどうしてこっちに来たのよ」K君は流れる汗を拭こうともせず「学園に居るより、こっちの方がおもしろいや」と答える。「こっちの方が辛いだろう」「いや。それに豚汁食えるもんな、エヘヘ」と笑う。K君とこんな他愛のない会話をかわしながら、手ごたえのある土を50センチ掘るのに30分もかかった。思えばK君は無断外出の常習者であった。家庭訪問をしてから嘘のように無断外出がなくなったが、そのK君が突然「園長、入園生と先生方の前で喋らせてくれ」という。「どうしてよ」と驚いて聞くとK君は「今まで無断外出して、入園生や先生たちに迷惑かけたから、お詫びするんだ。そして、2度と無断外出しないと皆の前で誓うんだ!」
感無量であった。
田園の山々に沈みゆく夕日を見つめながら、団地の奥さんたちが差し入れてくれた豚汁をK君は満足そうに何杯もおかわりしていた。
知的障害者の地域活動について
-
銀山市街地環境美化活動
重度の知的障害者が職員と力を合わせて、昭和52年から学園で作った花々をプランターに植え代えて、地域の主要街路地に飾っている。殺風景な農村の街路地は、急に生気を取り戻したように、色彩豊かな花々は、街全体をなごやかな雰囲気で包んでいる。
-
繁殖豚の種付け
中度の知的障害者たちは、昭和50年から職員と一緒に地域養豚家を訪れ、繁殖豚の種付けなどに参加をしている。当学園の養豚は、北海道家畜共進会で全道優勝を果たしている関係もあり、地元養豚家から大きな信頼を得ている。
-
公共施設・老人・母子世帯の家屋の除雪
軽度の知的障害者たちは、昭和46年から老人宅や母子宅の除雪を、町内会長の通報により行っている。ここ銀山地域は北海道でも有数の豪雪地帯として知られているが、雪が3日間も降り続けることがあり、すっぽり埋まってしまった家屋を・20人程の障害者がスノーダンプやスコップで除雪していく様は、まさに壮観である。
そのほか、無人駅になったJR銀山駅に、地元子供会や生徒会と共同で花壇をつくったり除草をしたりしている。また、中学生と共同で空きビン回収などをして、地元の児童とも融け合っている。
平成7年3月発行 ぎんざんだより103号
銀山学園長 野 村 健
福祉の里づくりを夢みて
21世紀が 障害がある人もない人も共に生きられる社会になることを願って
私のロマン-それは知的に障害をもつ人たちが、少しでも幸せになって貰いたいということである。その願いは誰もがもっている「幸せになりたい」と願う気持ちと同じであり、その願いが共に生きられる社会-福祉の里づくりへとつながっていったのである。
横路孝弘知事を囲んだ福祉の里づくり座談会
「春の陽の中、美しい水田の銀山にまいり、皆様から福祉と地域づくりに関するすばらしいご経験を伺い、久しぶりにすがすがしいひとときを過ごすことができました。
皆様の一言一言に感動しておりましたが、地域が施設を中心に発展してくる道のりは、決して平坦ではなかったのではないかとご推察申し上げます。
-中略-
今後は、銀山の活動を参考にしながら全道に広めてまいりたいと考えております。 後略」
-知事からのお便り・平成3年6月-
なにか目頭が熱くなる思いにさせられた。
横路知事さんの心のこもった文面とお人柄のなせる技なのだろう。
座談会の模様は、3新聞が報道してくれた。その見出しだけを紹介させてもらう。
・地域福祉の参考に 北海道新聞
-銀山学園 横路知事が視察-
・住民と福祉施設一体 北海タイムス新聞
-横路知事囲み 仁木町懇談会開く-
・視察の知事が絶賛 読売新聞
-地域と交流「すばらしい」仁木「銀山学園」-
座談会には、武田祐男後志支庁長(現北海道生活福祉部長)を始め、地域から15人の方たちが参加してくれ、それぞれの立場で入園者とのかかわりを通してまちづくりの話をして頂いた。
「園生を家庭訪問で受け入れてから、彼らのことが分かるようになり採用を決めた(銀山自動車整備工場)」「まわしを締め、裸で付き合って園生の気持ちが分かった」「銀山囲碁大会で園生が優勝している」など報告され、和気あいあいの中で終了した。時まさに平成3年5月23日、銀山学園史の一頁を飾ることになった。
自治省からモデルコミュ二ティ-に指定された今
古きを尋ねて新しきを知る(温故知新)という諺があるが、私は、古きを尋ねて新しきを創る(・・)という事が好きである。
ありがたいことには、私たちのささやかな地域活動が自治省に認められ、平成4年度北海道では1ヶ所、仁木町銀山(・・)地域(・・)がモデルコミュニティーに指定された。年間300万円、3年間の補助を頂けることになった。また、引き続き平成5年度には、銀山学園が道内で1ヶ所「ふれあいのまちづくり事業B型」に厚生省から指定され、年間350万円、5年間補助を頂けることになった。地域づくりに精を出してきた私たちに、新たな希望と勇気を与えてくれた。
これを機に地域づくりの中核の役割を果たしてきた銀山文化連盟を、銀山コミュニティ-推進協議会に名称を変え、活動内容もより充実させるために4つの部会を設けた。文化教養部会(従来の文化連盟)、文化イベント部会、福祉部会、多目的施設部会の4部会である。また、組織の若返りを図るため、私は還暦を迎えたのを期に、17年間務めさせて頂いた会長職を退き、名誉会長として蔭でお手伝いさせて頂くことになった。メンバーは、銀山地域にある23の団体、職域、クラブの代表と、10町内会の代表を含め、70人で今構成されている。
このような流れの中で、知的に障害のある人たちも、各種のイベントや生涯学習教室、文化祭など数多くの行事に参加して、地元住民と自然にふれあい、銀山住民としての市民権を得ていっている。
平成5年10月31日、作家小檜山博さん(泉鏡花賞受賞、芥川賞、直木賞候補作家)の講演を口火に、第1回銀山文化オリンピックの幕が切っておとされた。会場になった銀山小学校は、溢れるばかりの人々で賑わった。
前夜祭では、小檜山さんご夫妻を囲んで、町長はじめ地域活動家が銀山学園に集い、夜遅くまで寿司職人マーボちゃん(高橋賢文さん)の絶妙のにぎりを堪能した。
文化オリンピック本番では、銀山学園の入園者の作品(縫物)が、第2部で金賞に輝いた。金メダルは彼女にとって、生涯忘れえぬ宝物となることだろう。
地域こそ幸福実現をはかる原点
私の青春は、苦悩に満ちた灰色の青春だったが、ただ一つ誇れる青春の勲章があるなら、それは人類の尽くせテーマと言える「人間の幸福創造」を今なお考え、福祉の場を通してささやかでも実践させてもらっていることだ。
青春時代に感銘を受けたヘッセの「幸福」の詩は、悩んでいた私の魂に深い安らぎの境地を教えてくれたが、幸福実現をはかれる原点ともいうべき地域(・・)に目を向けさせてくれたのは、知的に障害をもつ人たちだった。
個人が一生懸命努力しても、個人の力だけで欲求を満たすことのできない知的障害者の欲求を満たせるのは、施設(・・)ではなく地域(・・)であった。
岡村重夫氏は、人間誰もが持つ社会的共通要求は7つあると私たちに教えてくれているが、そのひとつである職業的安定要求を満たすために、ふれあいレストランとドライフラワー共同作業所を、平成2年に後援会の援助で建設させて頂いた。今、レストランには卒園生3人が働いており、共同作業所では知的に障害の重い人たちが、地域の高齢者の方たちと一緒に作業をしている。作品は、JR札幌駅(パセオ)や新千歳空港の売店で売られている。道外では、新設になった神戸の新阪急デパートで常設コーナーを設けて販売されており、年1回の展示即売は、東京新宿小田急デパートや大阪阪急デパートなどで催されている。
今、福祉の潮流は、施設福祉から在宅福祉へ、そうして施設福祉も在宅福祉も包括した地域福祉へと変貌して行っているが、平成5年に札幌で開催された国際社会福祉セミナーで、三浦文夫先生(日本社会事業大学学長)は、日本を代表して基調講演を行った。その際、21世紀の日本福祉が進むべき期待像として、ケアリングコミュニティー(支え合う地域社会)の創設を提唱された。私も同感である。一方、日本の長寿社会構想を先駆的に提唱された医学博士で、日本ウエルエージング協会の会長をされている吉田寿三郎先生は「工業社会が子供を小産化し、抗生物質が人間を長寿にした。その結果、世界に類例をみない超高齢化社会を、いま日本は迎えようとしている」として、この状況を乗り越えるために、まず「自主自立と人間性の回復・高揚」が必要であるとされ、自ら理想的地域社会づくりを実践されている。私は、縁あってお二人の先生をそれぞれ銀山にお迎えすることができ、銀山地域づくりの有志と共に両先生から貴重なお話を伺う機会を得ることができた。
青春時代、幸福創造を願った私にとって、今の人間の幸福創造とは、人間の主体性が発露され、人間の共通要求が障害のある人もない人も自分も含めて、まず地域の中で満たされていくこと、換言すれば、共生社会づくりへの実践であった。
幸福創造への途は、置かれている立場や条件で多様であると思うのだが、私は福祉実践者として、また一住民として、いま身近に出来る(・・・)こと(・・)は、そこに住む人たちの共通要求が少しでも満たされ、心と心がふれ合える地域を創り出して行くことである。私には地域社会こそ幸福実現をはかれる原点だと思えてならない。
人間不在と呼ばれて久しい現代、人類の歴史の潮流は、21世紀に向かってまさに人間が人間として尊重できる日本の創造へと胎動し始めたのだと確信したい。そういう人間共生社会創造への情熱を燃やし続けることは至難の業である。しかし、座して論ずるだけではなにも生まれてこない。私はこれからも共感し合える人たちと共に、障害があってもなくても共に生きられる地域社会創造をめざして、歩み続けたい。
そこに人間が求めている幸福な社会が創出されていくことを夢みながら。
-完-